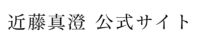彼が1歳半を迎える初夏の頃、風邪のような症状になり
近くの小児科を受診しました。
診断は予想どうり、風邪ですね…とのこと。
お薬をもらって、指示どうりに飲ませます。
そのお薬がなくなっても
一向に良くなった気配はなく、長引く風邪だなあと思いながら
また、同じ小児科へかかります。
またそのお薬がなくなっても
微熱は引かず、咳をしています。
3回目のお薬がなくなる頃
心なしか呼吸の仕方が気になりました。
赤ちゃんは、えてして呼吸の仕方が特徴的ではありますが
長男と3歳違う次男に、長男のその月齢の時のことを
思い出せないわたしがいます。
お医者さんが風邪だと言うわけですから
なんの疑いも持っていませんでしたが
どうしても何か気になり
いつもの小児科とは違う病院へ連れて行きました。
レントゲンを撮ってもらおうと思ったのです。、、、
初めて会話を交わすその誠実そうなお医者さんは
わたしに、とっても気を遣いながら
きっと言葉も選びながら
紹介状を書くから
大きな病院に行ってください
とおっしゃいました。
えっ?
というためらいは隠せませんでしたが
一刻もはやく!と、せかされているような気がして
意味もわからず車を走らせました。
聞こえた言葉は
『肺が片方機能していません…』
市内で最も大きな総合病院にそのまま受診したら
思いもよらぬことを言われます。
『今夜ひと晩ここで泊まって
明日そのまま大学病院に行ってください』と。
大学病院?ここじゃムリだということ?
どうしたらいいかわからず、不安と何かがごちゃ混ぜになって
あたふたするばかりのわたしは
何があっても動じないあの白髪のおじさんに連絡をしました。
おじさんは、仕事を終わらせるとそのままその病院にきてくれました。
明日、大学病院にいかなければいけないと伝えると
休みを取って送ってくれると言ってくれます。
頭が混乱しているわたしは、自分で運転して大学病院までいく自信もなく
送ってもらえることなにより助かったと思いました。
たまたま、彼は
その大学病院の小児科の教授と面識があり
その教授がどれだけ信頼できる人物かをわたしに教えてくれました。
翌日、一度も足を踏み入れたことのない大学病院なんていう
仰々しい建物に足を踏み入れました。
まだこの時は
その日に、家に帰れる…と思っていました。
ずいぶん長い時間待って
その、信頼できる教授の診察を受けます。
クマのような、あるいはカバのような
と言っては失礼ですが(笑)
まさにそんな風貌の教授は
ひとことふたこと、親であるわたしへの質問をしただけで
まだまだ歩き始めて半年くらいのその小さな身体を
黙ってあっち向けたりこっち向けたりしています。
何か言ってくれたらいいのに
黙ったままです。
ほどなく、今度は向かい合わせに座り
息子に、そのカバさんは聞きました。
『がんばれるか?』って。
その言葉だけでは
親のわたしはどう理解したらいいのかわからず
でも、どういう意味なのかを聞くのは
もっと怖い気がしたので
カバさんの次の言葉を待つしかありませんでした。
カバさんからは、結局どれだけの言葉も語られず
ただ、息子の顔を優しい笑顔で見ながら
『がんばれるか?』
って繰り返しました。
主治医…だという若い先生に呼ばれた時も
まだ『サイアク』…を想像できてなんかいないわたしでした。
『悪性リンパ腫』という単語と『ステージ3』
という単語だけは聞こえましたが
それが何なのか
その時のわたしにはまだ理解できていませんでした。
ただ、ただならぬ雰囲気でその大きな目を片時もそらすことなく言葉をこちらに向ける
その若い医師の真剣な表情から、ことの重大さを感じることはできましたし
いつの間にかわたしの目からは涙がポロポロこぼれ落ちていました。
隣を見ると
あのクールな白髪のおじさんまでもが
驚くことに涙ぐんでいるのです。
『抗がん剤…』という単語を聞いて
はじめて、息子の身になにが起こっているのか
そして、それを目の当たりにして
わたしがいかに非力であるのか…
テレビの中の世界の話だと思っていることが
いま、目の前で…そう、他でもない我が身に起こっていて
まったく頭も働かず、なんの決断もできず
ただ…揺れ動く気持ちを、どうやって落ち着かせたらいいのか
いえ、もしかしたら
それさえも考えられなかったかもしれません。
その日から
ゴールのさっぱりわからない息子と二人の旅が始まりました。
白血病とガンの子供しかいないその病棟は
そんな重大な病名であるにもかかわらず
ほとんどが6人部屋です。
唯一ある個室は
『無菌室』という部屋で
そこに入って、その後元気に病棟に戻ってきた子を
わたしは思い出すことができません。
そんな個室なのです。
一歳半と言えば、言葉も少しずつ覚える頃。
女の子ほどおませではありませんが
それでもようやくわずかな会話が成り立つかどうかという
そんな頃です。
最初に話せるようになった言葉が
『てんてき…』って、どう思います?
その単語を自慢げに話す息子をどんなに不憫に感じたかしれません。
こんなところにいなければ
こんな言葉は知らなくて済んだのに…と。
嫌がるお薬を飲ませ…
親はその部屋には絶対に入れてもらえないという
泣き声だけが廊下まで聞こえる検査を受け
手も足も、もう点滴を入れるところがないからと
小さな胸に穴を空け
髪の毛は抜け落ち、別人かと思うほど顔が浮腫んで
笑わなくなった息子を見ながら
一人欠け、二人欠け…する病棟で
その頃のわたしは
何かをポジティブに考えるなんていうこともまったく知らず
祈ること…なんていうことも知らず
毎日毎日…
黄色い点滴液が規則正しく落ちていき
その量が少しずつ減っていく…その様子ばかりを
ボーッと眺めていました。
どこが痛いのか、どこが気持ち悪いのかを
まだ言葉で表現することのできない彼は
不機嫌になることだけが唯一の抵抗であり、わかってほしいことだったのだと思います。
ある日のこと
同じ病室で仲良くしていた男の子のところに
真夜中に、看護師さんが数人慌てて出入りしたかと思ったら
日が昇り、明るくなった病室には
もうその姿はありませんでした。
同じ病室の中でみんなで寝ているのですから
なにが起こったのかは
一目瞭然です。
おめでたい退院ではない
そのお別れは
今日の昼間まで仲良くしていたお母さんも
もちろんその子供である息子のお友達も
まったくの無言で音もなくその部屋から姿を消します。
それ以外の5人の母親達は、誰もが目を覚ましたはずです。
でも、静かに見送るしかすべがなかったのです。
かける言葉なんか、見つかるはずもありません。
そんな時、必ずと言っていいほど
次はうちの子の番か…と、思わなくてもいいことが頭をよぎります。
両親しか入れない…というその病棟では
土日になると、お父さんが交代で泊まりにきます。
お母さんを休ませてあげるためでしょう。
ああ、わたしには
土日に代わってくれる人はいませんでしたわね。
共有できる人もいません。
子供の前では決して見せることのない涙を流せる場所もありません。
そう、休みの度に
トーマスかドラゴンボールのオモチャを買って
お見舞いに来てくれる白髪のおじさんだけが
泣き言を言える相手だったのかもしれません。